会社勤めなどしていたら、
例えば、販売なら販売だけを担当し
マーケティングならマーケティングだけを担当します。
しかし自宅で教室を開くと、つまり個人事業主になると
あらゆる業務を一人でこなさなければなりません。
自宅教室経理の仕事
その中で大切な仕事の一つに「経理」があります。
前田は父の代からの付き合いの税理士さんに
領収書は必ず取っておくこと
小遣い帳みたいなものでいいので、
必ず毎日支出と入金を記帳すること
と教わりました。
経理というと、おもに確定申告のために、
税金を払うためにお金の流れを記帳する、
と思われるかもしれませんが、
実はそれだけではないのですね。
それに関しては項を改めるとして、
ここではまず、経理の基礎、
「帳簿記録」つまり「簿記」に良く使う、
仕分けの勘定科目を載せておきます。
前田の教室あんぷらぐどの男性ピアノ講師は、
弥生会計というパソコンソフトを使っています。
一度設定すると、大変使い勝手がいいらしく、
確定申告もこれで大丈夫!と豪語しています(笑)
もちろんわからないところは税務署まで足を運んで
きちんと確認していますが。
自宅教室でよく使う勘定科目
前田は確定申告は税理士さんに任せています。
その税理士さんが確定申告で使っている、
貸借対照表や損益計算書によく出ている勘定科目を集めました。
個人自宅教室では、日々の記帳は、
資産負債関係(貸借対照表 B/S)の勘定科目より、
収益費用関連(損益計算書 P/L)の勘定科目がよく使われます。
簡単にいうと「必要経費」ですね。
◆租税公課:国税と地方税国地方公共団体などから課せられる税金 自動車税、固定資産税など
◆広告宣伝費:不特定多数の人を対象に行う広告宣伝のために支出する費用
◆地代家賃:工場や店舗などの土地建物の賃貸にかかわる費用 月極駐車場代など
◆水道光熱費:水道電気ガス灯油などのエネルギー費用 冷暖房費、空調代
◆接待交際費:取引き先や自社の従業員その他の関係者等に対する接待、慰安、贈答などに支出した費用
◆旅費交通費:通勤や業務上の移動に伴う交通機関の利用料や出張に伴う支出
◆消耗品費:業務で使用する少額の資産、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満
事務用品費も含まれる場合がある
◆事務用品費:文房具、伝票類の費用
◆通信費:電話料金や郵便料金など通信に要した費用。インターネットプロバイダー料金回線使用料など
◆保険料:生命保険の保険料や火災保険などの損害保険の保険料など
◆修繕費:壁の塗り替え、床の張り替え、保守管理費、パソコン修理代など
◆支払い手数料:金融機関や社外の専門家への手数料不動産業者への仲介手数料など
士業、コンサルタントへの報酬
◆新聞図書費:業務に必要な情報などを経るための新聞書籍雑誌などの購入費用
◆教材費等
◆講師料
◆減価償却費:固定資産の取得価額を耐用年数(使用可能期間)に火を配分するときに計上。
減価償却累計額の相手科目。
減価償却費
ここで一番分かりにくいのが減価償却費だと思います。
例えばピアノを500万で買ったとします。
前田の教室で使っているピアノはもっと安いのですが笑、
税理士さん作成の書類を見ると、耐用(使用)年数が10年となっています。
ピアノは買った年だけで使用するのではなく、
何年にもわたって使用するものです。
これを購入した初年度で費用として全額計上するのでなく
10年にわたって価値を減らしてゆく、つまり費用計上していくということです。
分かりやすくかなりおおざっぱに言って
初年度 50万費用計上 残450万円分の価値
2年度 50万費用計上 残400万円分の価値
・・・
前田の場合、ほかに内装防音工事や、
AV機材・設備も固定資産になりますので、
減価償却されています。
まとめ
経理の仕事の本質は「現金の管理」です。
簡単に言えば、儲かっているのかいないのか?
これをしっかり把握するための「資料」です。
この管理が、いわゆる「どんぶり勘定」になってしまっては
教室経営の財政状態がわかりません。
収入や支出を正確にきちんと記録することで、
教室経営の業績や財政状態を把握し、経営分析を行い、
未来への経営計画に役立てることもできるのです。
地味で面倒な「作業」かもしれませんが、
毎日コツコツと「習慣化」していきましょう!
【自宅教室ひとことアドバイス 6】
※必ずしも本編と内容が一致しているわけではありません。
2割のお客さんが、
その店の8割の売上を占める。
といわれます。
2割のお客さんの、そのまた2割に
「受講したい!」と思わせる、
隠れた裏メニューともいうべき、
「高収益(=高単価)レッスン」
を「隠れ目玉レッスン」として
用意しておきましょう。
これが芸術2割の部分になります。

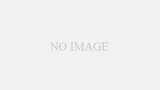

コメント